2012年07月27日
農作物の読みは「のうさくぶつ」か「のうさくもつ」か
最近、テレビやラジオのアナウンサーが農作物を「のうさくぶつ」と言っていました。
違和感をなかなか拭うことができません。
昔、学校の先生は確かに「のうさくもつ」と教えていました。
辞書を引くと、作物「さくもつ」は「田畑で栽培する農作物」で、
「さくぶつ」と呼ぶ場合は「文学・美術上の作品」ということになっています。
例を挙げると、園芸作物・工芸作物・商品作物の場合は「さくもつ」、
工作物・著作物・創作物の時には「さくぶつ」となるわけです。
それならばなおさら、「のうさくもつ」と読むべきだと思います。
ある解説では、「農作+物」と考えて、「著作+物」と同様に、
「のうさくぶつ」となるように書かれていますが、
こじつけのような感じが否めず、なかなか腑に落ちないのです。
「畑作物(はたさくもつ)」が「畑+作物」であるように、「農作物」も「農+作物」とすべきではないでしょうか。
あるいは、「農業作物」の省略形とするのが自然だと思います。
1989年発行の国語辞典には、「のうさくぶつ・のうさくもつ」、どちらの読みも載っています。
1997年出版の広辞苑にも両方載っています。

2000年頃に国語審議会で「のうさくぶつ」限定になったのでしょうか。
いずれにしても、どちらか1つにするなら「のうさくもつ」の方がすっきりするのですが、
どうやら正解は「のうさくぶつ」に絞っているようです。
よろしければクリックをお願いします
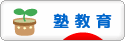
にほんブログ村
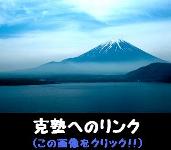
違和感をなかなか拭うことができません。
昔、学校の先生は確かに「のうさくもつ」と教えていました。
辞書を引くと、作物「さくもつ」は「田畑で栽培する農作物」で、
「さくぶつ」と呼ぶ場合は「文学・美術上の作品」ということになっています。
例を挙げると、園芸作物・工芸作物・商品作物の場合は「さくもつ」、
工作物・著作物・創作物の時には「さくぶつ」となるわけです。
それならばなおさら、「のうさくもつ」と読むべきだと思います。
ある解説では、「農作+物」と考えて、「著作+物」と同様に、
「のうさくぶつ」となるように書かれていますが、
こじつけのような感じが否めず、なかなか腑に落ちないのです。
「畑作物(はたさくもつ)」が「畑+作物」であるように、「農作物」も「農+作物」とすべきではないでしょうか。
あるいは、「農業作物」の省略形とするのが自然だと思います。
1989年発行の国語辞典には、「のうさくぶつ・のうさくもつ」、どちらの読みも載っています。
1997年出版の広辞苑にも両方載っています。

2000年頃に国語審議会で「のうさくぶつ」限定になったのでしょうか。
いずれにしても、どちらか1つにするなら「のうさくもつ」の方がすっきりするのですが、
どうやら正解は「のうさくぶつ」に絞っているようです。
よろしければクリックをお願いします

にほんブログ村
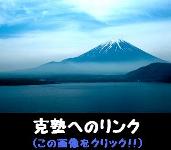
Posted by ベンジャミン at 12:38│Comments(9)
│言葉の意味・語源
この記事へのコメント
こんにちは。検索で辿り着きました。
「のうさくぶつ」の件、私もずっと違和感を抱いていました。
Yahoo知恵袋の解説で尤もらしく“「農作」した「物」”なのだと書かれていましたが、随分と都合のいい分解の仕方だなあと思います。
「NHKでは“のうさくぶつ”と読んでるんだから、それが正解なのだ」という風潮は如何なものかと思います(むしろNHKだからこそマズいと思うぐらいでないと)。
個人的には、自分の違和感を大事にして今後も「のうさくもつ」と読むつもりです。
突然の訪問、失礼いたしました。
「のうさくぶつ」の件、私もずっと違和感を抱いていました。
Yahoo知恵袋の解説で尤もらしく“「農作」した「物」”なのだと書かれていましたが、随分と都合のいい分解の仕方だなあと思います。
「NHKでは“のうさくぶつ”と読んでるんだから、それが正解なのだ」という風潮は如何なものかと思います(むしろNHKだからこそマズいと思うぐらいでないと)。
個人的には、自分の違和感を大事にして今後も「のうさくもつ」と読むつもりです。
突然の訪問、失礼いたしました。
Posted by chuyo at 2016年02月07日 15:08
農作物という言葉の成り立ちを考えればわかることです。
「のうさくもつ」という読み方をするならば作物に農がくっついて出来たものになります。しかし、作物という言葉はその時点で農作物と同じものでわざわざ農を付ける意味がありません。
「のうさくぶつ」という読み方をするならば農作に物がくっついて出来たものになります。これは、工作物や創作物のような〇〇して出来た物という言葉と同様の成り立ちであると推測できます。
よって、「のうさくぶつ」の方が正しいでしょう。
「のうさくもつ」という読み方をするならば作物に農がくっついて出来たものになります。しかし、作物という言葉はその時点で農作物と同じものでわざわざ農を付ける意味がありません。
「のうさくぶつ」という読み方をするならば農作に物がくっついて出来たものになります。これは、工作物や創作物のような〇〇して出来た物という言葉と同様の成り立ちであると推測できます。
よって、「のうさくぶつ」の方が正しいでしょう。
Posted by 名無し at 2016年04月27日 12:45
創作物と農作物の熟語構成が両方とも○○+○なんていわれたら気持ち悪い
Posted by ふにふに at 2016年05月11日 15:27
農作+物の人は「耕作物」とでも言っていれば良いのに。
創作や工作ほど、農作は一般的な用語じゃないでしょ
いろんな○作という単語が生まれてきたから、出てきたから「作物(さくもつ)」の前にわざわざ「農」をつける必要が出てきたのでは?と考えています。
だから、農に作物で「のうさくもつ」
決して農作+物ではない
創作や工作ほど、農作は一般的な用語じゃないでしょ
いろんな○作という単語が生まれてきたから、出てきたから「作物(さくもつ)」の前にわざわざ「農」をつける必要が出てきたのでは?と考えています。
だから、農に作物で「のうさくもつ」
決して農作+物ではない
Posted by 通りすがり at 2016年05月12日 18:44
あれ、どっちだっけ、と検索してこのページを拝見しました。
昭和40年代生まれですが、確か学校では「農作物」は「ぶつ」で「作物」は「もつ」と習ったように思います。ややこしくてかえって印象に残ったのですが、それでもいまだに時々わからなくなっています。
自分としては、日本は古来農耕民族であったので「作物」といえば田畑でできるものであったところが、比較的新しい時代になって「農作による生産物」の意味で「農作物」という用語を作ったのではないか、と考えてこのややこしさに自分なりの決着をつけています。「工作物」「著作物」「創作物」は明らかに「工作・著作・創作された、物」ですが、これらは、文化の発展とともに、特に近代の行政や立法の中で多様な生産物を表しわける必要が生じ、生み出された語なのではないでしょうか。「農作物」という語にも同じ背景や成り立ちを感じます。
ただ、ややこしくて不便なことには変わりありませんから、この語については87年の辞典や93年の広辞苑のように両方認めておけばいいんじゃないかなあ、と思います。
昭和40年代生まれですが、確か学校では「農作物」は「ぶつ」で「作物」は「もつ」と習ったように思います。ややこしくてかえって印象に残ったのですが、それでもいまだに時々わからなくなっています。
自分としては、日本は古来農耕民族であったので「作物」といえば田畑でできるものであったところが、比較的新しい時代になって「農作による生産物」の意味で「農作物」という用語を作ったのではないか、と考えてこのややこしさに自分なりの決着をつけています。「工作物」「著作物」「創作物」は明らかに「工作・著作・創作された、物」ですが、これらは、文化の発展とともに、特に近代の行政や立法の中で多様な生産物を表しわける必要が生じ、生み出された語なのではないでしょうか。「農作物」という語にも同じ背景や成り立ちを感じます。
ただ、ややこしくて不便なことには変わりありませんから、この語については87年の辞典や93年の広辞苑のように両方認めておけばいいんじゃないかなあ、と思います。
Posted by r at 2016年08月30日 12:56
(さくもつ)とは農作業で得る食べ物のことで、それに農をつけるのは(頭が頭痛)と言っているようなもの。工芸作品を(さくもつ)とは言いません。
(のうさくもつ)は本来誤りです、しかし残念ながら既に市民権を得ているようです。
(のうさくもつ)は本来誤りです、しかし残念ながら既に市民権を得ているようです。
Posted by 権兵衛 at 2020年02月19日 13:05
今晩のNHKのニュースでものうさくぶつと言ってました。
違和感を覚えました。
違和感を覚えました。
Posted by まさまさ at 2020年03月24日 21:57
のうさくもつ派がこれほど多いとは義務教育の敗北ですね。
間違いを教えた先生がひとりであっても大勢の教え子がそのまま覚えてしまう、
のうさくぶつと読めない馬鹿を増やした罪は非常に重い。
のうさくもつ派は一生恥を晒し続けることになるでしょう。
間違いを教えた先生がひとりであっても大勢の教え子がそのまま覚えてしまう、
のうさくぶつと読めない馬鹿を増やした罪は非常に重い。
のうさくもつ派は一生恥を晒し続けることになるでしょう。
Posted by 名無し at 2020年03月28日 19:59
最初に覚えたものとは違うから違和感を覚えるのであって、違和感を基準に正誤を判断するのはいけません。
私も「のうさくもつ」と教わり、「一(いち)段落」は「ひとだんらく」と教わりました。他の人が違う読み方をしてるのに違和感を覚え調べたら間違いだと知り覚えなおしました。時々こんがらがるので調べなおしますが。
例えば自分はちゃんと学んだのに覚えてない人たちが間違ったまま押し通して一般化されるのはとても不愉快です。「代替(だいたい)」を「だいがえ」と読むのが間違いではないなどと言われたらすごく嫌です。モヤモヤします。勉強しなかった人たちが勉強した人の努力を台無しにしてるようでたまりません。
しかし、言葉は生き物なので厳密な正解はないのかもしれません。それでもあえてどちらが正しいかはっきりしてほしい、ということならば辞書に最初に出てくる読み方のほうが良いのでしょう。
ちなみに「山茶花」は「さざんか」と読みますが、もともとは「さんさか」だったらしいです。字を見てもそのほうが納得します。いずれは「雰囲気」も「ふいんき」が正しくなるかもしれませんね。嫌ですが。
私も「のうさくもつ」と教わり、「一(いち)段落」は「ひとだんらく」と教わりました。他の人が違う読み方をしてるのに違和感を覚え調べたら間違いだと知り覚えなおしました。時々こんがらがるので調べなおしますが。
例えば自分はちゃんと学んだのに覚えてない人たちが間違ったまま押し通して一般化されるのはとても不愉快です。「代替(だいたい)」を「だいがえ」と読むのが間違いではないなどと言われたらすごく嫌です。モヤモヤします。勉強しなかった人たちが勉強した人の努力を台無しにしてるようでたまりません。
しかし、言葉は生き物なので厳密な正解はないのかもしれません。それでもあえてどちらが正しいかはっきりしてほしい、ということならば辞書に最初に出てくる読み方のほうが良いのでしょう。
ちなみに「山茶花」は「さざんか」と読みますが、もともとは「さんさか」だったらしいです。字を見てもそのほうが納得します。いずれは「雰囲気」も「ふいんき」が正しくなるかもしれませんね。嫌ですが。
Posted by ぬるま湯 at 2021年04月19日 11:25











